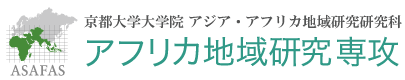*インタビュアー:K
K:よろしくお願いいたします。
重田:どうぞよろしくお願いします。
K:まず研究内容について教えてください。

重田:私の研究は、「アフリカの○○学が専門です」というようにはっきり言い切れないところがあります。あるときは「アフリカの農業を研究しています」と言いますし、時には「アフリカの作物の起源について研究しています」と言うこともあります。場合によっては「文化人類学です」「民族生物学です」と言ってしまうこともあります。アフリカで研究していることについて、ディシプリン(専門分野)を断言してしまうのは、私にとってはとても難しいことのようです。だからこそ、この大学院に籍を置かせてもらっているのかもしれません。
K:先生の研究には、いろいろな視点があって面白いです!学生の時には何を専門に学んでいらしたのですか?
重田:大学では農学部でアフリカ起源のシコクビエという雑穀を栽培して、草丈や種子の重さを計ったりして遺伝的な変異の研究をしました。でも、アフリカに関心をもったのは、それよりもずっと前です。
K:研究のためにアフリカに行かれたわけではなかったのですか?
重田:学部3年生の夏(1978年)にザイール(現在の国名はコンゴ民主共和国)に渡航したのが最初です。大学生の仲間たちと『日本—アフリカ学生交流』というプログラムをたちあげて、ケニアとザイールを訪問しました。まず数日ケニアに滞在したあと、ケニアでナイロビ大学の学生と活動するグループと別れた私たちのグループは、ザイール大学キンシャサ・キャンパスの学生といっしょに約一ヶ月間国内を旅しました。
K:それが、最初のアフリカ経験だったのですね。その後、どうされたのですか?
重田:当時、私は、現在大阪大学におられる栗本英世さんと、国立民族学博物館(民博)におられる吉田憲司さんの3人で、学生交流プログラムとは別に野外科学研究会という組織をつくってスーダン南部(最近、南スーダンという新しい国になりました)で民族学的なフィールドワークをする準備をすすめていました。3人はもともと当時の教養部におられた米山俊直先生の研究室で文化人類学の講義や演習を通じて知り合った仲間でした。当時、民博におられた福井勝義先生(故人)には、スーダン行きの準備の段階から現地に着くまで大変お世話になりました。
学生交流プログラム活動を終えた後に、私は日本には帰らず、再びケニアに戻って約2か月のあいだ、スーダンに行く準備をしました。メンバーが日本から来る前にナイロビからジュバまで飛行機で行き、そこからナイル川の東側にあるトリットという町まで予備調査に出かけたのが、いまから思えば私の最初の生のアフリカ経験だったと思います。その後、翌年の3月に帰国するまで僅か半年ほどの滞在期間でしたが、今でもそのときに体験したことは鮮明に覚えています。
K:学生交流とフィールドワーク研究って、すぐにはつながらないような気がするのですが、そもそもどうして、アフリカに行こうと思われたのですか?
子供の時に読んだ本の影響もあってか、大学に入ったらアフリカに行きたいと思っていました。でもその一方で、1970年代当時私たちの世代には、研究とは何なのか、「豊かな国」の私たちが、いわゆる「開発途上国」に出かけて、研究をするといって一方的に調査をするのでよいのだろうか、などと考えていた人が少なからずいたと思います。大学紛争はそろそろ下火になってきていましたが、それでも高校生や大学生が(全員ではありませんが)世界と自分たちとのつながりかたや、社会でおこっている様々な出来事に無関心ではなかった時代だったと思います。その後、日本の状況もアフリカの状況もどんどんと変化していますから、今の学生さんたちはあまりそういうことを考えないでいられるのかなと思いますが、私たちの世代は、社会の矛盾について何かを考え、よく議論していました。その中で立ち上がったのが、先ほど言った『日本—アフリカ学生交流』というプログラムでした。
当然、アフリカに対するロマンはありました。アフリカの大地に立ってアフリカの風に吹かれてみたい、アフリカの人々に会ってみたい、といった気持ちがあった一方で、圧倒的な力に押しつぶされていくふつうの人々、特に当時はベトナム戦争の記憶がまだ生々しく残っていて、戦争の災禍にあう人びとの姿が映像を通じて様々に届けられた時代でしたから、そういったローカルな人々を研究対象にして、論文を書いて、出世していく仕事に対する疑問や葛藤もあったんです。研究に対する後ろめたさは、今でも常にあります。
『日本—アフリカ学生交流』というプログラムは、そんな葛藤がある中で、まずはアフリカの同世代の人たちと直接会って話したい、そういった思いから作られました。そもそも彼らと対等になるのは無理なことなのかもしれませんが、調査や研究ではなく学生同士なら通じ合えるところがあるのではないかという期待がありました。何よりも、アフリカを遅れた地域として援助や開発の対象としかみなさない日本の風潮に異議を唱えて、違うことをしたいという思いもありました。
そこで、私たちは様々な日本紹介のプログラムを用意していって、現地の学生に盆踊りを踊って見せたり、日本の様子をスライドで見せたりしました。でも、私たちの甘い期待はすぐに打ち砕かれました。ザイールの首都キンシャサでは地元のラジオ番組に出て、インタビュアーに「フランス語も満足にできないのに、どうやって交流するの?」とつっこまれて、言葉を失いました。
ケニアでもザイールでも、彼ら学生は日本をとても発展した国だと認識していました。でも日本が急速に工業化した裏には公害に代表されるような弊害もあったわけで、そのことを伝えようと私たちは水俣などの話をしたんです。ところが、質疑応答の際にナイロビ大学の学生に「だから何なのだ。自分たちの国に、あなたたちの国のように発展するなと言いたいのか。国が発展するのなら、公害だってウェルカムだ。」と言われて、とっさに返答に窮することがありました。それまでは開発や援助というものに対して懐疑的で、「それで本当に現地の人たちが幸せになるものなのか」という素朴な疑問を抱いていた私にはけっこうショックなことでした。同年代の学生のこういった考えや言葉に直面すると、環境を破壊するとされる大規模な開発にさえ単純に反対することはできないと感じるようになりました。それまではなんとなくアンチ開発のスタンスをとっていたのですが、必ずしもすべての開発が人々を苦しめるのではなく、よき開発を求めている人も少なからずいることを考えなくてはならないと思いました。そういうことをいろいろと考え始めると、フィールド研究なんてできないのです。でも、そこが私の少しずるいところなのですが、いろいろと考え悩みながらもとりあえず「両方やってみればいい」「できることからやってみよう」と決めました。それに、本当のところは彼らがどう思っているのか、もっと親しくならないとわからないのでは、とも考えたからです。
最初のフィールド調査では、スーダン南部のアチョリという人々の村に住まわせてもらい、植物を採集して、その名前や利用方法、植物にまつわることわざ、歌などを聞いてまわりました。それをまとめたのが、私の最初の論文です。物に即して研究を進める、たとえば植物採集のように物のデータを集めて、それをもとに研究を進めていくのがアフリカセンター流のやり方ですが、私もそのようにして研究していたのです。
学部生のときは植物遺伝学を専攻していました。研究室では主に小麦とその近縁種を対象にした研究がおこなわれていましたが、私はアフリカ好きの変人みたいな扱いをされていたので、私だけ特別に、別の講座におられた阪本寧男先生の指導をうけてアフリカの雑穀についての研究をさせてもらいました。シコクビエという雑穀を小麦畑の横で栽培して、それについての研究で卒論を書きました。当時、そういうことを自由にさせてもらえたことに、今でもとても感謝しています。
修士では、経団連の海外派遣学生への奨学金をもらって2年間ケニアのナイロビ大学農学部作物学修士課程に行きました。その奨学金は、偶然その年から第三世界に行く学生も特に支援するというものだったのですが、あるとき学生研究室にやってきた指導教員の先生が、皆の集まっている大きなテーブルの上にポイと投げたその応募書類がスーッと滑ってきて私の前で止まりました。もう、運命だなと思いましたね。諸先輩が欧米の大学に留学するなかで、私はこれで幸運にも2度目のアフリカへ行くことができました。
修士論文でも、やはりシコクビエの研究をしました。ナイロビ大学の指導教員はジャガイモの専門家でしたが、快く好きなことをさせてくれました。9ヶ月のコースワークが終わってしばらくしたころ、ケニアでクーデター未遂事件が起こり、大学は半年間休校になってしまいました。その期間をつかって村を訪問しながらいろいろな品種の種を集めました。大学が再開し、ビクトリア湖の近くの試験場を使わせてもらえることになって、そこで集めたシコクビエの比較栽培試験をしました。しかし、留学を延長することはできず、京都に戻ってシコクビエの研究で修士論文を書きました。

その後、アフリカでの農業研究のプロジェクトに入れていただき、今度はエチオピアでエンセーテという植物の研究をしました。今までは種子の小さな雑穀を研究してきましたが、次は趣向を変えてイモの研究をしてみようと思ったわけです。それだけでなく、スーダンやケニアの農村を訪ねているうちに、農業という営みについて、人が植物を利用しているという見方だけでは一方的で、植物も人を利用しているという見方をすることもできるのではないか、と考えるようになりました。博論では、このような「人—植物関係論」と私が呼んでいるアイデアがあって、エンセーテと現地の人々が取り結ぶ様々な関係を明らかにしようと考えました。
最初にお話したように、大学では専門分野に分かれて研究するということが当然のようにおこなわれていて、それはそれで非常に妥当なというか、だからこそ学問が進んできたと思うのですが、私自身は、アフリカという土地やそこに住んでいる人々のことを深く理解したいという思いで研究をしようとすると、ひとつやふたつの専門分野だけでは理解しきれないことがたくさんでてくるのではないか、と思っているのです。誤解をまねく言い方かも知れませんが、もっと雑多なことにも目を向けて、いろいろな見方に考えを広げてみることで、新たに見えてくるものが少なくないと考えています。地域研究という場は、そういう私にはうってつけのところだと思っています。
学生時代の研究の話だけでは、アフリカの作物について農学の研究をしているだけのように聞こえるかもしれませんが、じっさい私の興味はいろいろな方向に向いています。『日本—アフリカ学生交流』の経験から、現地の人々がよりよく暮らすということはどういうことなのかに強い関心を持つようになりました。日本に帰ってからは、以前にもまして人類学や開発学の勉強をするようになりました。今、「実践的地域研究」と私がいっていることも、このころの体験にすべてつながりますね。もっとも、最近では睡眠文化研究なんていう全く毛色の違うこともやっていて、私の研究内容は実に「雑」がいっぱいなんです。
K:地域研究をしていくうえでは、そういう「雑」って大切だと思います。でも、その「雑」を研究として扱うのはとても難しいですね。
重田:はい、そのとおりです。そのうえ地域研究っていうのは、何かを明らかにしてもそれがその地域でしか通用しないものではないかという指摘をよく受けてしまいますね。何か確固とした専門分野の研究だと、そういわれることは少ないでしょう。でも、だからこそ、地域研究はやりがいのある研究分野だと思っています。私には、個別の事象の深い理解や観察から、何かの普遍的な理解に至りたいという、そういう指向というか、願望があるからだと思います。でも、それとは全く反対のことを言いますが、比較的小さな人びとの集まりが幸福であるためには、どうすればよいのか、人や物や事の関係がどのようであればよいのか、それをアフリカの村で考え実践していくことに大きな意味を感じていて、普遍なんてどうでもいいと思っている私もいます。
私が今すすめているテーマの中に「在来知とコミュニティの研究」というものがあります。「在来知」というのは、単純な知識のリストやデータベースではなく、今そこにいる人々が生きるための武器として操作している様々な知識の動態といえます。これを便宜上いくつかに分類して、それを同じ場と時間を共有する研究者が一緒に研究したり観察して記述したりして、情報を集め共有することで現地の人々の考え方に接近しようというものです。そうすることで、今まで不可思議で理解できなかった事柄も理解できるようになるかもしれない。そうすれば、これまでの「開発」にみられた一方的な押しつけも、誤解も偏見もなくなるのではないかと思っています。
これまで私の個人的な関心として紹介した「人—植物関係論」についても、「実践的地域研究」についても、話し出せばきりがないのですが、それぞれのテーマ理解の深め方を編み出して、それを地域研究のツールにしていこうというのが、在来知研究の方向性のひとつで、共同研究的なテーマとなっています。研究関心は千路に乱れ、あまりまとまりはありませんが、あえて整理すればこうなります。でも、基本はアフリカの人びとのことを深く知りたいということですね。
K:関心はいろいろな分野にわたっていますが、一貫してアフリカという土地や人々を理解したいというお気持ちがあるんですね!ありがとうございました。
K:フィールドでの写真を1枚紹介していただけますか。
重田:1枚の写真というより、コラージュ写真ですが、エチオピアのフィールドで、村の人々に家で栽培しているエンセーテの品種を持ち寄ってもらった時にとった記念写真です。
調査村の一角に土地をもらって、エンセーテの在来種を保存しようというプログラムをおこなっています。その方法として、村の集会の際に「みんなのエンセーテを集める場所を作りたい。これからなくなってしまう品種が出てきたときに、ここに来ればその品種が手に入るという環境を作りたい。子どもや孫の世代にエンセーテの品種を伝えることができる。」と説明をして、村の人たちに自分の畑にある品種を持ち寄ってもらっています。持って来てくれた人には、そのお礼として、持って来てくれたエンセーテと家族と一緒に撮った写真をプレゼントすることにしていて、その時の写真を集めたのが、この写真になります。

現在は58品種600個体集まっています。自分で集めているのではなく、村の人に持ち寄ってもらっているので、集まり方はゆっくりかもしれませんが、まだまだ増えると思います。年に一度、エンセーテを持って来てくれた人たちを招待して、お祭りを開催しています。その際に、一番多くの品種を持って来てくれた人には記念品を渡したりしています。在来種を集めている圃場ですが、みんなの集まれるスペースにしたかったので、囲いをつけませんでした。村の人は「この品種はある?」といってちょこちょこ顔を出してくれますし、子どもたちの遊び場や村人のおしゃべりの場としても機能しています。この間からは、別の圃場に各品種を増やして、欲しい人にあげられる環境を整えています。
どうしてこのような試みをしているのかというと、いろんな理由がありますが、いまや少なくなってきている人たちの大切にしている作物だから、その多様性を維持して、彼らの生活を支援する活動がそのようなものかと考えたときに、この方法が一番フィットするのではないかと考えたからです。今のところ、フィットしているというのかはわかりませんが、近所の村でも、これと同じものを作りたいという要請があって、少しずつ広まったりしています。そういう反応をみると、受け入れられているのかなと思っています。先ほど言ったように、人々の交流の場にもなっていますしね。
圃場はオープンなスペースですので、いつでも誰でも入れます。エンセーテの品種名を彫って焼いた土器を置いていたのですが、ある日、村の子どもたちが遊んでいるときに、石を投げつけて土器を全部割ってしまったのです。これが村の会議で取り上げられたのですが、最初は土器を割ってしまった子どもの親に弁償させるという話だったのですが、話しあっているうちに「村のみんながガードマンにならなくてはならない。みんなでこの圃場を守ることが必要だ」という話になりました。これは想定していなかったことなのですが、こういった効果があるんだなとも思いましたね。
K:囲いのない交流の場ができたことで、いろいろな効果がみられるのですね。村のみんなのための場所という認識が彼らの中に芽生えたことはうれしいことですね。次回の調査の際は、何も事件が発生していないといいですね(笑)
K:最初に調査地に行った時と現在で最も変わった点を教えてください。

重田:最初にエチオピアの村に入ったのは1986年ですが、その時は道路なんてなくて、歩いてアリの村々を回りました。当時は茅葺の屋根ばかりだった住居は、トタン屋根になりましたね。でも一番の変化は、どの季節でも使える道路ができたことですね。ある日、農作業から帰ってきたおじさんが「神を見た!」と言って興奮していて、何かと聞いてみたら、ブルドーザーが大きな岩や木を動かしながら道路を作っているのを見たようなのです。村の人々は自動車なんて見たこともない、当時はそんな時代で、一番近くの都市まではバスと歩きで10時間かかっていたのですが、今では1時間半で行けるようになりました。
道ができたことにより、警察署ができ、病院ができ、小さいですがホテルまでできました。人が動き、物が動くようになったのです。農業省の役人の車もどんどん来られるようになりましたから、改良品種の普及なんかも簡単にできるようになったわけです。そういう点をみても、やはり在来種の保存は大切だなと思っています。
外部社会とつながるということは、他を巻き込み、受け入れていくというプロセスがあるわけですよね。太陽電池の使い方の講習会なんかもおこなわれるようになりましたしね。新しいものへのアクセスが急に良くなって、人びとがそれを取捨選択するチャンスがあるとは思いますが、その情報量とスピードの増え方は急激ですね。
情報量の増加でいえば、携帯電話の普及も面白いです。ここもアフリカ各地と同様に携帯電話が入ってきていますが、エチオピアでは中国企業が独占的にアンテナを立てて、電気のないところにも太陽電池を利用した中継基地を立てているので、首都のアディスアベバから村の近くのジンカという町までは全部携帯がつながるようになりました。うちの村はちょうど電波が弱い地域で、みんな携帯は持っていますが、村の丘の上に行かないと使えないのです。丘の上まで行くと世界とつながるわけです。村の人は電話をかけるときに「携帯の丘」の上に集まります。不思議な光景ですよ(笑)
そうやって新しいものが入ってくるときの姿というのは、私が小さいときに道路が少しずつ整備されていく様子を見たり、スーパーマーケットというものができたときに見に行ったりした時の感覚と一緒なのだなと思います。そういった感覚を、エチオピアの人たちは短期間に一気に経験しているんだなと感じますね。
K:日本では徐々に経験してきたものが、アフリカでは一気に経験している光景がみられるので、変な感じがします。
重田:日本が経験した近代化とも、全然違う順番で近代化が進んでいますしね。携帯なんて、日本の近代化ではずっとずっと後の方にできたものですが、アフリカでは電気が来る前に携帯が来るという光景があちこちで見られます。我々日本人からすると信じられません。
でも、そんな急速な発展にうまく対応しているアフリカの人たちは、すごいなと思います。その吸収力には驚きです。近代を一気にまとめて受容する人たちの姿は、とても面白いです。それもまた、研究の興味のひとつになりそうですね(笑)
K:またひとつ、重田先生の興味を増やしてしまいました(笑)急速な近代化に対応するアフリカの人々のパワフルさは、私も調査のたびにすごいなと感じています!
K:アフリカ専攻の特徴を教えてください。
重田:もちろんアフリカに関心のある人たちがいるわけですけど、その関心の種類にはいろいろあります。アフリカ専攻はあらゆる関心の幅を受け入れることができるだけの「ゆるさ」がありますね。どのような興味を持った人であっても、来るものは拒まずで、受け入れます。それゆえに、期待したものと実際の中身が違うこともあると思います。そういった意味では、「使い手はある、活かせば資源」といった感じの面白い場ではあります。
みんなが同じ方向を向いているわけではないので、特徴が語りにくいですね。特に最近はその傾向が強いです。以前は生態人類学とか広い意味での進化論という背骨がありましたから、もう少し方向性にまとまりがありましたが、今はアフリカのことをよりよく理解するという共通項しかないと思います。「なんでもあり!」がアフリカ専攻の特徴だと言ってしまうと、返ってここに来にくくなるかもしれませんね(笑)
K:そんなアフリカ専攻の学生に求められるものは何でしょうか。
重田:「なんでもあり!」というところに来るからこそ、学生に求められることは「こういうことがやりたい!」というものを一本もって、強い信念のもと研究を進めることが求められるのではないかと考えられるかもしれませんが、これは全く逆です。先ほどの「雑」の話にもつながってきますが、状況を対応的にふるまえて、何が一番自分にフィットしていて、何が今この時代に一番面白くて、何をすることがこのアフリカ専攻のリソースを一番活かせるのか、ということを来てから考えてほしいなと思います。そういった柔軟性を持ちつつ、一番自分がやりたいと思えることを、いろんな人の助けを借りながらやり遂げていくことができる人がここに来ると、ハッピーになれるのではないかと思います。
しかし、そういう環境というのは両刃の剣といいますか、迷子になってしまう人が出てしまうという危険性もあります。そうならないように、私たちが気をつけていなければいけないのですが、でもそれを強く誘導しないというのが、ここのもう一つの特徴だと言えます。そういったある程度の自由さを求めてきている人もいるし、ある程度のレールをひいてもらって、そのスピードや景色を楽しむことを求めている人もいるのだということが、最近わかってきました。でも基本は、「脱線を楽しむ」というか、線路の上だけを走るのではなくて、いろんな景色をいろんなところで見ながら、いろんな分野の知識とか経験を取り入れて、ひとつ自分の決めた目標に向かって進んでいく。そして論文を書いて学位をとる。そういった形が理想ではないですかね。
K:脇目を振りながらの一点突破ですね!
重田:難しいですけどね(笑)言うは易く、やるは難しです。だから、京大のそういったやり方は、ある種の玄人技で、誰でもできることではないといって批判されることもありますが、それは誤解だと思います。プラモデルを組み立てるわけではないので、マニュアルなんてものはないのです。相手が生身の人間や変化する地域で、そのことを理解しようとするときに、マニュアルを求めること自体が少し違うと思うのです。サグラダファミリアのように、現在進行形の作業というものが、その時々に見せるキラッと光るものが我々の作品であり、我々の研究するうえでの喜びだといえます。こういった研究に完成なんてものはありません。つまり、「永遠の共同作業に、あなたも参加しませんか?」ということです。
K:わぁ!ロマンですね!!!
重田:ロマンですよ!ただ、そういってしまうとアフリカの人たちがどこかに飛んでいってしまったように聞こえてしまいますね。生身の人間を相手に、考えたり、作業をしたり、行動したりっていうことは、とても大変です。積み上げられて、前の職人の残したものにさらに付け足していくサグラダファミリアと違うところは、研究対象が刻々と変化する人や環境ですので、今まで培われてきたものが通用しなくなる可能性があるという点です。そういう意味では、単純な積み重ねではないということも理解しておいてもらえるといいと思います。
よく「学部の頃からアフリカに行っている人にはかないませんよ。」と言われることがよくあるのですが、それは全然そんなことはなくて、今この時点でアフリカに関わろうという人たちの視点の方が、昔の錆びついたロマンにしがみついている人たちの視点よりずっと鋭いと思います。だからこそ、アフリカに関わりたいと思う若い人たちに、どんどん来てほしいですね。